ポリネーター・フレンドリー・ガーデニング
第2章
「ハナアブとの出会い」
↑2013/03/19 菜園に咲く菜の花。
2002年にこの里山に移住した時から、ニホンミツバチの養蜂をやってみたいと考えていました。当時はネコのミロク、ビッチ、ラティ、ウリ、ミカ、マル、ポメラニアンのまりちゃん、ウサギのモモとルンルン、ニワトリ、チャボ、アイガモ、金魚たちも一緒に暮らしていたので、これ以上家族を増やすと、世話が大変かなと考えて思いとどまりました。
とりあえずミツバチが好む蜜源植物を植えて、いつでも養蜂が始められる準備をしておくことにしました。あとで知ったんですが、これが欧米で「ビー・フレンドリー・ガーデニング
Bee friendly gardening」と呼ばれているものでした。
「ビー Bee」は、日本では一般的に「ミツバチ」と訳されます。Google翻訳でもミツバチと訳されますが、原語の「ビー Bee」は、ミツバチを含む多様なハナバチのことであって、ミツバチのことだけを指す言葉ではありません。ミツバチを指す場合は「ハニービー
Honey bee」です。
けれどマルハナバチやクマバチ、その他大勢のハナバチの認知度が極端に低い日本の場合、「ハナバチ」といってもイメージがわかない人が多い。という私こそ、そうでした。
ミツバチなら言葉として知っているので、「ビー Bee」はハナバチと訳されず、ミツバチと訳されてしまうのでしょう。現状、ハナバチは日本語として通用しない言葉です。

↑2013/03/19 当時の菜園の様子。
画面の上部の中央に畝を作っています。ジャガイモを植えつけようとしていたかも知れません。今(2025年)は、菜園の4分3は、薔薇と果樹と花木と草花の庭に生まれ変わっています。当時は、ほとんど野菜畑で、そのまわりに果樹や花木、草花やハーブ類を植えていました。
2002年に移住して10年の月日が流れて、もともと田んぼだったところがこんな菜園に生まれ変わりました。 私は美しいと感じるんですが、こんなの畑じゃない、雑草ばかりじゃないかと思う方もあります。上の写真の白いのはナズナ。ピンク色はホトケノザの花の色です。
グランドカバーするのに、わざわざ園芸種のグランドカバープランツを栽培しなくても、種もまかず、水やりも肥料も必要なく、多様な野生の植物がこうして自然に生えてくるのはありがたいことだと思います。
農薬や除草剤を使用しない家庭菜園は、こんなふうに雑草と共生させることで、病害虫に負けない健全な野菜が育ちます。多様な植物、微生物、昆虫、カエル、鳥たちが共生することによって、一種類の害虫だけが大発生するようなことがなくなります。
栽培する野菜の生育のことだけを考えるのではなく、菜園の環境全体にとりくむことが「ガーデニング」だと思います。そしてガーデンを通して私たちが忘れている「大地、地球、自然」をとりもどしていく・・・
英語の「ガーデン Garden」は、庭、庭園、菜園、花園、小さな果樹園を意味します。家庭菜園はガーデンの範疇です。
広大な農園、農場、果樹園は「ファーム Farm」です。経済効率を考えて一種類の作物を大量に栽培する必要があります。商品としての見栄えをよくするために化学肥料や農薬が必要かも知れません。



↑2013/03/19 ホトケノザがあんまり美しいので撮っておいたのだと思います。 田んぼだったところなので、最初のころは水はけが悪く、イネ科の雑草スズメノテッポウ(ピーピー草)ばかりが生えてきました。
土が改善されてくるとホトケノザやナズナ、オオイヌノフグリ、カラスノエンドウなどが増えてきて、スズメノテッポウが姿を消していきました。

↑2013/03/19 菜園の雑草、ナズナ(ペンペングサ)。


2013/03/09 オオイヌノフグリ。


2013/03/30 カラスノエンドウ。

↑2013/03/19 エンダイブ。私は雑草と一緒に育っている様子が美しいと感じます。

↑2013/03/19 エンダイブ。

↑2013/03/19 エンダイブ。

↑2013/03/19 カツオ菜。種をまくのが遅かったのでしょうか、まだカラダが小さい。 こういう育ち方をしている野菜は本来の香りがあって味が濃い。スーパーマーケットに並んでいるふつうの野菜とは違います。


2013/03/12 カツオ菜の様子。

2013/03/12 ホウレンソウの様子。
私は2013年にこんなことを書きました↓
家庭菜園は次のような歓びと学びをもたらしてくれます。
1.種まく歓び、発芽の神秘に立ち合える歓び、双葉子葉が開き、本葉(大人の葉)が育って行く自然の不思議な成長力に立ち合える。
2.スーパーマーケットの買い物では、商品として大きく成長したものしか入手できないが、家庭菜園をやると、小さな間引き菜を順次収穫して頂くことができる。
実は間引き菜は美味しい。
3.自分で育ててみることによって、今では多くの人が知らない“野菜の旬”を知ることができる。
4.販売するわけではないので、農薬や化学肥料を使わなくてもよく、安心で美味しい食べ物が得られる。
流通のプロセスを経ないで、菜園から台所へ直結しているので、もっとも新鮮な食材が得られる。
5.土に触れることで、忘れていた大地・地球とのつながりを取り戻すことができる。
6.野菜栽培を通して、様々な雑草や昆虫や微生物の存在に気づき、関わるようになる。 雨や光や空気が違う意味を持つようになる。抽象概念でしかなかった「自然」がリアリティを持つようになり、内的にも自然と調和した生き方を求めるようになる。それが結果的に身体的・精神的・スピリチャルな健康をもたらしてくれる。
7.自分で種をまいて、野菜の成長のプロセスを見まもるからこそ、その命をいただくことへの“感謝”の気持ちが自然に生まれる。現代人が忘れている感謝の念を思い起こすことができる。

↑2013/03/19 ところがとにかく、飛来するはずのミツバチが一匹もやって来ない。例年ならとっくにブーンという羽音で菜園が賑やかになるはず。レイチェル・カーソンの『沈黙の春』を思い出しました。絶対におかしい。何か大きな異変が起きているのかも知れないと不安になりました。
その頃、ミツバチのことばかり考えていたけれど、ブーンの羽音がしないということは、他のハナバチもハナアブも飛来しなかったということです。

2013/03/30 菜の花の様子。ミツバチはまだやって来ない。ただこの日、下の2枚を撮りました↓

2013/03/30 1枚はピンボケでした。今ならニッポンヒゲナガハナバチのメスだとわかります。当時私はニッポンヒゲナガハナバチのことも知りませんでした。

もう1枚はこれです。これはいったい誰だろう? みたいな感じだったと思います。ニッポンヒゲナガハナバチだったんです。

↑2013/04/04 ミツバチを待ちくたびれた2013年4月4日、ようやく飛んできたと思って喜んで撮ったのが上。 写真中央部に写っています。うれしかったので、もう少し近よって撮ったのが下↓

↑2013/04/04 その日私はミツバチを撮ったつもりでした。ところが夜、パソコンで拡大してショックを受けました。あきらかにミツバチではない。

↑Google検索してみると、どうやらアシブトハナアブというハナアブの仲間らしい。2013年4月4日のブログは「ミツバチが来ない」と題して、この写真をアップしてこう書きました。
菜園の小松菜の花に来たハナアブの仲間(たぶんアシブトハナアブ)。 ハナアブやモンシロチョウは来るんですが、ミツバチが来ません。

↑2013/04/04 その時撮った写真をパソコンで拡大して見ると、上のアシブトハナアブとは違う個体も撮っていた。 シマハナアブ♀です。

↑2013/04/04 この子はシマハナアブのオスだと思います。ミツバチだと思って撮ったら、ハナアブを撮っていたんです。その日のブログにこんなことも書いています。
今年、初めて日本ミツバチを飼う試みをするつもりでした。が、これだけの菜の花を用意しても一匹の姿もありませんでした。日本ミツバチも西洋ミツバチも。
ミツバチがやって来ないこともショックでしたが、自分がミツバチとハナアブを混同していたことにもショックを受けました。自然豊かな里山に暮らして約10年もたつのに、先入観でものを見ているというか、ちゃんと観察していないというか・・・多くのことがそうなのかも知れないと思い知りました。
菜の花にブーンという羽音が聞こえたら、即ミツバチと決めこんでいたかも知れません。よく見たらハナバチやハナアブの仲間だったのかも知れない。
ただ、この子たちはみんな小さいうえに、すばやく飛んで、じっとしていないのでじっくり観察できない。2013年4月4日夜、私は「写真判定」の必要性を痛感しました。これ以降、ハナバチやハナアブたちの写真が増えていきました。
そうして庭を撮った写真が多数たまってしまい、アップできないままDropboxに保存することになってしまった。
ともかく「2013年4月4日」という日付と「アシブトハナアブ」は、私の新しい出発点になりました。

↑2013/05/01 その年、そのごも毎日菜の花の様子を観察したけれど、ミツバチはやって来なかった。 ぜったいにおかしい。5月になってもミツバチが現れないなんて。

↑2013/05/05 菜の花の様子。花の盛りは終わり、種をつくるプロセスに移っています。

↑2013/05/05 ようやくやって来たニホンミツバチ。

↑2013/05/05 アシブトハナアブもいました。もう肉眼でも間違いません。 が、確かに肉眼で見ていると間違っても無理はないと思います。ごくごく小さい上にすばやく飛ぶひとたちだから。
だからFacebookやブログで、「ミツバチが花にやって来ました」という記事にハナアブの写真が載っているのをちょくちょく見かけます。

↑2013/05/05 この日、菜の花でツチイナゴも撮りました。オシベやメシベ、花弁もムシャムシャ食べているようです。ツチイナゴは幼虫のときも大人になっても菜食主義者です。

ツチイナゴの後姿。

ツチイナゴは私たちの庭で一番よく見かけるバッタです。

↑2013/05/05 菜園で菜の花が咲くと、様々な生物がうるおいます。これはコアオハナムグリ。花粉を食べています。

↑飛び立とうとしているアオハナムグリ。2013年5月5日のブログにこう書いています。
もう菜の花は刈り取って、何かの種をまくか苗を植えつけるかしたいと思っていたのですが、ミツバチだけでなく多様な昆虫が集まってくるので、刈るのはもう少し先延ばしするしかないかな・・・
そうとは知らず「ポリネーター・フレンドリー・ガーデニング」をやっていました。
菜園で野菜を栽培すると、料理の直前に必要なだけ摘みます。根っこから抜かないで、必要分だけ葉を摘んでいくと、新鮮な野菜を長く収穫し続けることができます。「摘み菜」といいます。これが家庭菜園の醍醐味です。
根っこを抜かないと、コマツナでもシュンギクでもそのうち花が咲いてきます。ふつうは採種用に少し残し、あとは刈り取って土にすき込むか、堆肥にするかします。
そうして次の何かを植えたいところなんですが、ポリネーターたちのレストランとして花を残す考え方、それは「ポリネーター・フレンドリー・ガーデニング」の方法論でした。
キャベツでもハクサイでもブロッコリーでもカリフラワーでも何でも開花します。その甘い花蜜や栄養豊富な花粉を求めて多様な生物が集まります。
次章ではそういう子たちことをもう少し詳しくお話したいと思います。植物の受粉(ポリネーション)については、高校2年の生物で習うらしいですね。私は全然記憶がありません。
たぶん授業がつまらなくて、空想にふけっていたのだと思います。次に描く絵のことをあれこれ思い浮かべることもありました。退屈しのぎに先生の似顔絵を面白おかしく描いて、まわりのクラスメイトにちらっと見せたりもしました。クラスメイトが思わず吹きだして、あやうくバレそうになったこともあります。
そんな私がポリネーションやポリネーターについて語る立場ではないんですが、仕方がありません。「ポリネーター・フレンドリー・ガーデニング」とGoogle検索しても、感心するようなサイトが出てこないので私がやるしかないと思いました。
“Pollinator friendly gardening”で検索すると、いくらでも素敵なサイトが現れます。海外にはいっぱいあるんです。動画もいっぱいあります。日本はいったいどうなってしまったのでしょう?

↑2013/05/05 ともかく、2013年5月5日にミツバチが現れたことで、その日のブログにはこんなことを書いています。
今年から日本ミツバチの「養蜂」をやりたいと思っていました。このぶんならやれそうです。
ミツバチが5月になっても現れないことをずいぶん心配し、やきもきしたというのに、2013年5月5日の時点では「やれそう」と書いています。そうとうやりたかったのだと思います。
でもそのあと私は養蜂を思いとどまりました。まず第一に、これほど菜の花がたくさん咲いているのに、5月5日になるまでミツバチが現れなかった原因がわからないことです。
次に、ミツバチとハナアブを混同するほど無知であること。養蜂をやるなら、もっと自然のことを学んでからでも遅くないと思いました。
私がやりたい養蜂は、私が愛するネコや犬を可愛がる感覚であって、少しハチミツを分けてもらえたらうれしいけれど、ハチミツをたくさん採取して売ろう、みたいなことを考えていたわけではありません。
ミツバチが大変な努力をしていることは知っていました。ひとりのミツバチが一生かかって集められるハチミツの量は「ティースプーン1杯」だと、本もネットにも書いてあります。
家庭菜園の延長、庭先養蜂というべき最小の養蜂を構想していました。それも犬やネコを可愛がるノリだとしたら、そういうのは「養蜂」とは言わないのかも知れません。
庭でニワトリを数羽飼っているからといって「養鶏」とは言わないみたいに。
それと2013年4月4日にニホンミツバチとアシブトハナアブを混同していることがわかってから、それまであまり考えたことのなかった他のハナバチやハナアブのことを意識するようになりました。

↑2013/05/05 シロツメグサで吸蜜するコマルハナバチ。

2013/06/12 ウツボグサ(セルフヒール)に吸蜜にやって来たトラマルハナバチ。
すばやく動き、さっと飛び去る小さなハナバチやハナアブを一眼レフで、どう撮影したらいいのかわからず、ピントが合わないケースがほとんどでした。上の写真みたいに、かんじんのトラマルハナバチが画面からはみ出ていたり。
たくさん撮るわりには、使い物にならないのが多すぎ。シャッター速度をあげてみると今度は画面が暗くなるだけで、やはり使い物にならないのが多かった。
使い物にならないというのは、Webサイトやブログ、Facebookでは使えないという意味で、何でも撮っておけば「写真判定」に使えることはわかりました。そのうちこんなことを考えました。
ニホンミツバチの巣箱を庭に設置すると、ひとつの巣箱に5000匹から2万匹も入るという。すると他のハナバチやハナアブたちはどうなるのだろう?
働き者のミツバチと競合して勝てるハナバチやハナアブなんていないと思います。彼らはこの庭から去っていくに違いない。去ってもかまわない。この地方は自然が豊かで雑木林もたくさん残されているので何も困らないでしょう、そこで暮らしていけると思います。
ただ私の場合は・・・知名度の低いマルハナバチや、その他大勢のハナバチ、人気のないハナアブたちのことを身近に観察するのが私の役割だろうと思いました。
2013年晩春、「ニホンミツバチと家族として暮らす庭」をあきらめ、「多様なハナバチ、ハナアブたちと家族として暮らす庭」を作っていくことにしました。
ミツバチについてはたくさんの人が情報発信もされているけれど、ミツバチ以外のハナバチやハナアブについては極端に情報量が少ない。どこか公園や自然の豊かなところに出かけて、ハナバチやハナアブの素晴らしい写真を撮るかたはあります。
でも自分の庭で蜜源植物を育て、そこに食事にやってくるハナバチやハナアブを家族として歓迎し、家族として暮らそうという発信は、2013年当時もなかったし、今もほとんど無いようです。だから私がやるしかないと思い立った次第です。
単なる「物好き」と思われることもありますが、自分の庭でポリネーターたちを守ろうという発想は、近年“Pollinator friendly gardening”として世界的に普及し、世界には数えきれないほどの発信があります。
ハナバチのために住まいまで作ってやる人が増えています。スウェーデン発祥のインテリア家具店のイケアは単独性ハナバチのための「ビー・ホーム Bee Home」のデザインを考えています。
国際連合食糧農業機関(FAO)は「世界ハナバチの日」(2019年5月20日)に、ハナバチたちのホテルを作るよう市民に呼びかけました。 世界中でハナバチたちのためのさまざまな住まいが考案されています。
そのことはあとの章で話題にするとして、2013年晩春に養蜂を思いとどまったおかげで、現在に至るまで多様なハナバチやハナアブと家族として暮らすことができ、家族写真をたくさん撮ることができました。
そして2021年には、アメリカ合衆国バージニア工科大学植物環境科学部の研究者による次のような科学論文を目にしました↓
» 「ミツバチの巣箱は、野生のハナバチの個体数、種の豊富さ、そして農場の果物の数を減少させる」
やっぱりそうだったんです。ミツバチの巣箱を設置することで、他のハナバチたちの個体数と多様性を減少させるという研究結果です。ということはきっとハナアブたちの個体数と多様性も減少すると思います。
ハナアブやハナバチはどこかに去って行くだろうからいいとして、農産物が減少するというのはこれは意外です。いったいどういうことでしょうか?
ついでに、ナショナル ジオグラフィックの最新のNEWSをリンクしておきます↓
» 「養蜂で野生ハナバチ8割減か、餌めぐる競争が離島の実験で判明。飼育ミツバチを閉じ込めてみた、結果を受け養蜂を停止、伊ジャンヌートリ島」( 2025/06/25配信)

↑2006/06/24 オオキンケイギクにやって来たナミハナアブ。私は長いあいだキャノンのコンパクトデジカメを愛用していました。小さいのでいつも持ち歩いてメモ代わりに何でも撮っていました。この写真もそうです。撮るのは撮ったものの、たいして興味は無かったと思います。

2006年当時、私もポリネーターたちの大切なお仕事のこと、理解できていませんでした。養蜂を始めようとしていた2013年春の段階でもわかっていなかったと思います。

2006/06/24 これ「蝿が手をすり足をする」の姿です。まったくハエです。 ハエが好きな人はあまりないと思います。
一茶の俳句「やれ打つな蝿が手をすり足をする」は驚きです。こんな句を作るのは一茶しかないでしょう。私にもハエを敬遠する気持ちがあって、何となくハナアブのことも敬遠とまでいかなくても、積極的には興味を持たなかったと思います。
ところが近年、ハナアブさえ著しく減少してきたと感じるようになり、注意して観察しているうちに、しだいにいとおしくなってきました。1cm前後しかない小さな生命が、けなげに生きている。彼らを守ってやりたい気持ちが強くなってきました。

この口、ハエそのものです。感染症を媒介するイエバエのイメージを引きずってしまうと楽しくない。たぶんそのせいでハナアブは人気がないのだと思います。
欧米には、ハナバチ Beeの大きな「Facebookグループ」があります。私も数年まえから1.3万人もの会員を持つオーストラリアのFacebookグループ“The
Buzz on Wild Bees”に加入しています。
ハナアブ Hoverflyの「Facebookグループ」はほとんどありません。日本には完全にありませんが、欧米でもほとんどないようです。唯一といってもいい“Hoverflies
of the World”は会員5000名のイギリスのグループで、最近私も加入しました。
上の2006年6月24日撮影のナミハナアブの写真なんですが、オオキンケイギクの花で食事しています。この北米原産のオオキンケイギクがこの年2006年2月1日、環境省が定める外来生物法に基づき特定外来生物と指定されたんです。
こんなふうにナミハナアブの食料となっている花だし、これを栽培し続けたかったんですが、栽培したら何と3年以下の懲役や300万円以下の罰金をくらうという。私は2006年6月24日のブログでこう書きました。
このオオキンケイギク、北米原産でこのごろあちこちでよく見かけます。 確かに繁殖力が強い。私たちは近くの野山で雑草化していたのを畑に持ち込んだのでした。
生命力が強いとは思ったけれど、特別に 環境破壊するほどの植物だとは思いませんでした。というのは 問題にするなら、もっともっと問題にすべき生物がいるからです。
特別に環境破壊する、といえばこれはもう間違いなく人間だと思います。人間の文明に対する警告こそ緊急に必要です。生態系破壊を指摘するなら、オオキンケイギクではなく私たち自身の思考や欲望や生活形態や経済体制を問うべきでしょう。
私は近くエンジェルファームのオオキンケイギクを抜き取ります。でも本当は私たちこそ、抜き取られてもおかしくないことをしています。
ちょっと悔しかったけれど、オオキンケイギクを処分しました。少なくともオオキンケイギクはナミハナアブたちにとって素敵なレストランでした。 ベニシジミたちにとっても↓

↑2006/06/24 オオキンケイギクはベニシジミやナミハナアブにひどいことをするわけではありません。花蜜や花粉を提供する素敵なレストランなんです。人間はベニシジミやハナアブにひどいことをします。あらゆる生物に対しても。

↑「人間のせいで生物が絶滅する・・・自然界の危機は人類の危機」(BBC)
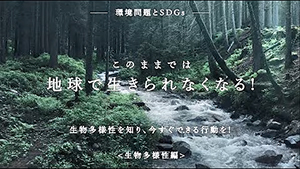
↑環境問題とSDGs【生物多様性編】(大分市環境局)
人間はオオキンケイギクを「日本の侵略的外来種ワースト100」に選定しましたが、人間こそ地球生態系の破壊者ナンバーワンだと思います。
オオキケイギクを栽培しても販売しても、3年以下の懲役や300万円以下の罰金だという一方で、「世界の侵略的外来種ワースト100」に選定されているホテイアオイがホームセンターでふつうに販売されています。
私が処分した2006年からずっとオキンケイギクがどうなるか見てきましたが、年々生息地が増える一方です。多年草ですからエンジン草刈り機で刈っても株が生き残ります。
もはや帰化植物として定着し根絶不能なレベルに達したと思います。
多くの自治体のWebサイトが「除草剤を使用することが可能な場所であれば、除草剤による駆除も効果的です」と記述しています。
侵略的外来種と指定されている植物はオオキンケイギクだけではありません。それらすべてを根絶するとなったら、すさまじい量の除草剤が必要になるでしょう。その方が深刻な生態系破壊だと思うんですが・・・
長野県安曇野(あずみの)市のWebサイトはオオキンケイギクについてこう記述しています↓
環境保全の観点から、除草剤はなるべく使用しないようにお願いします。他の植物を枯らしてしまったり、薬剤が周辺環境へ飛散して悪影響をおよぼす恐れがあります。
やむを得ず使用する場合は、水路・河川への流出、住宅・田畑への飛散に十分な配慮をした上で、薬剤が目的とする植物以外にかからないよう注意して使用してください。

↑2006/06/22 玄関先でくつろぐウリ。オオキンケイギクで食事するナミハナアブの写真と同時期です。こういう子たちと一緒に暮らす感覚で養蜂を考えていました。家族感覚です。

↑2006/06/17 庭石の上でくつろぐウリ。彼女はここに移住した2002年にここで生まれ(ラティと野良猫のボスの間にできた子。
妻がヘソの緒を切りました)、2019年12月にここで亡くなりました。
老衰でした。
ウリたちみたいに、ミツバチをふくむハナバチ、ハナアブ、蝶、甲虫、バッタ、鳥たち・・・花のレストランを利用する生物たちと家族のように暮らすこと、
それを「ポリネーター・フレンドリー・ガーデニング」と呼びたいと思います。









